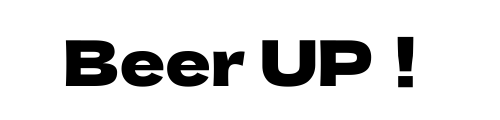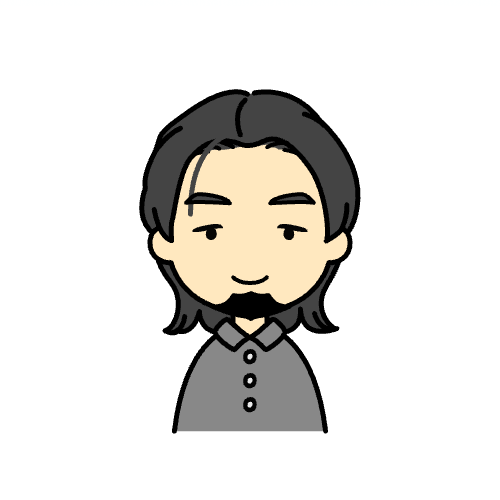最近、飲食店やスーパーでも、クラフトビールを見かける機会が増えてきました。
こうした中で、クラフトビールに興味はあるけれど、「種類が多すぎてよくわからない」「地ビールとどう違うの?」と感じたことはありませんか?
この記事では、クラフトビールの定義や種類、選び方のポイントまで、はじめての方にもわかりやすく解説していきます。
クラフトビールの定義と特徴
クラフトビールとは?どんなビールを指すの?
クラフトビールは、小規模な醸造場(ブリュワリー)が独立して造る、こだわりと個性に満ちたビールのことを指します。
日本の法律上は「クラフトビール」という言葉に明確な定義はありませんが、業界団体である全国地ビール醸造者協議会」は、小規模かつ独立した醸造所が造る、個性豊かなビール」と表現しています(出典)。
一方、アメリカの業界団体「Brewers Association(全米ブルワーズ協会)」は、以下の3つの条件を満たすものをクラフトビールと定義しています。
• 小規模(Small):年間生産量600万バレル以下
• 独立(Independent):大手酒類企業が資本の25%以上を保有していない
• 伝統的(Traditional):伝統的もしくは革新的な製法・原料を使用
出典:https://www.brewersassociation.org/statistics-and-data/craft-brewer-definition/
こうした定義をもとに、日本でも「味」「香り」「個性」を大切にしたクラフトビールが全国で親しまれています。
クラフトビールの定義をより深く理解するためには、「ビール」そのものの分類やルールも知っておくと役立ちます。
クラフトビールと地ビールの違いとは?
「クラフトビール」と「地ビール」はよく似た言葉ですが、意味合いは少し異なります。
| クラフトビール | 地ビール |
|---|---|
| アメリカ発の概念 | 日本の地域振興施策から登場 |
| 品質・個性重視 | 地域性・観光要素が強い |
| 全国に流通し、ブランド化もされる | 特定の地域のみで流通することが多い |
しかし現在では、「地ビール」もクラフトビールの一種と見なされるケースが多く、明確に線引きされることは少なくなっています。
クラフトビールが人気を集める理由
クラフトビールは、単なる「飲み物」としてだけでなく、造り手の想いや個性が感じられる“体験型”のビールとして人気を集めています。
豊かな香りや多彩なスタイル、飲む場所やペアリングによっても印象が変わるのが魅力です。
また、地元のブルワリーや限定醸造など、“一期一会”の特別感もクラフトビールならでは。「自分の好きな1本を見つける楽しさ」が多くのファンを惹きつけています。
クラフトビールの種類と味の特徴
クラフトビールの魅力は、なんといってもその多様なスタイルと味わいの幅広さにあります。
同じ「ビール」でも、使われる原料や製法によって、香り・苦味・色・アルコール度数がまったく異なります。
ここでは、代表的なスタイルと味の決め手について紹介します。
主要スタイルの紹介(IPA /スタウト/ヴァイツェンなど)
クラフトビールには100種類以上の「スタイル」が存在します。中でも代表的なものを以下に紹介します。
| スタイル名 | 特徴 |
|---|---|
| IPA | ホップの苦味と柑橘系の香りが強い。ガツンとした飲みごたえ。 |
| スタウト | 色が黒く、ローストされた麦芽によるコーヒーやチョコのような香ばしさが特徴。 |
| ヴァイツェン | 小麦を使った白ビール。バナナのようなフルーティーな香りで、苦味は少なめ。 |
| ペールエール | バランスの良い苦味と香り。クラフトビールの中でも最も親しみやすいスタイルの一つ。 |
| セゾン | フルーティーでスパイシー。ドライな後味があり、夏にぴったり。 |
これらはあくまで一例で、各ブルワリーが独自のアレンジを加えているため、同じスタイルでも味わいは異なります。
スタイルごとの味わいの違いは、飲み比べることで実感しやすくなります。下記の記事では、定番から個性派まで幅広く紹介しています。
ビールの味を決める3つの要素
クラフトビールの「味」は、主に次の3つの原料によって決まります。
• モルト(麦芽)
→ 甘みやコク、色味の基礎をつくる。焙煎の度合いによってキャラメル風味や香ばしさが生まれる。
• ホップ
→ 苦味の元。IPAなどでは柑橘・トロピカル・松の香りを加える重要な要素。
• 酵母
→ アルコールを生み出すだけでなく、香りや風味(例:フルーティー、スパイシー)にも大きく関与。
これらに加え、水のミネラル成分や副原料(フルーツ・スパイスなど)も、味に影響を与えるす。
同じビアスタイルでも、使用する原料の配合によって全く異なる個性が出るのがクラフトビールの醍醐味です。
モルトやホップの種類によって、香りや苦味のバリエーションが大きく変わります。原料の特徴について詳しく知っておくと、ビール選びがもっと楽しくなります。
クラフトビールのアルコール度数はどれくらい?
クラフトビールのアルコール度数(ABV:Alcohol by Volume)は、スタイルや醸造所によって大きく異なります。
一般的には4%〜7%程度が中心ですが、なかには10%を超える“ハイアルコール”なビールも存在します。
| スタイル | 度数の目安 |
|---|---|
| ヴァイツェン | 約4.5〜5.5% |
| ペールエール | 約5.0〜6.0% |
| IPA | 約6.0〜7.5% |
| ダブルIPA | 約8.0〜9.5% |
| インペリアルスタウト | 約9.0〜12.0% |
日本でお馴染みのビールのアルコール度数は、5%前後ですので、そのイメージを持っていると、クラフトビールの度数の幅広さに驚くかもしれません。。
アルコールが強めのビールは香りや甘みもしっかりしていることが多く、飲みごたえのある一本を楽しみたい人に人気です。
どこで買う? クラフトビールの購入方法
今ではスーパーやネット通販でもクラフトビールを気軽に楽しめる時代になりました。
とはいえ、「どこで買うのがベスト?」「種類が多くて迷う…」と感じたことはありませんか?このセクションでは、購入場所ごとの特徴とおすすめの選び方をわかりやすく解説します。
コンビニやスーパー、酒屋で手軽に購入
クラフトビールに興味を持ち始めた方にとって、最初の入口としておすすめなのがコンビニやスーパーや酒屋です。
「スプリングバレー」や「TOKYO CRAFT」など、全国流通している定番のクラフト系商品を手軽に試すには、近所のコンビニ・スーパーを見てみるのが良いでしょう。
また、地元の酒屋や専門店に足を運べば、ブルワリー直送の商品や地域限定ビールとの出会いも。スタッフと会話しながら選べるのも、実店舗ならではの魅力です。
ネット通販で全国のブルワリーにアクセス
クラフトビールの種類や地域性をもっと楽しみたいなら、ネット通販の活用が断然便利です。
各ブルワリーの公式サイトでは、その醸造所ならではの限定商品や飲み比べセットなどを販売しています。
また、以下のようなクラフトビール専門ECサイトでも、全国の銘柄をまとめて注文可能です。
• クラフトビールオンライン
• クラフトビアーズ
• Best Beer Japan など
一部では定期便やギフトセットも用意されており、家にいながら多彩なビールを体験できるのが大きな魅力です。
クラフトビールが飲めるお店・ブルワリー
「まずは味を試してみたい」「いろんな銘柄を少しずつ飲んでみたい」そんなときは、クラフトビールを提供するお店や直営ブルワリーを訪れるのもおすすめです。
以下のようなスタイルで楽しむことができます。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| クラフトビールバー/ビアパブ | 10〜20種類以上のビールが揃う。飲み比べセットやペアリングメニューも充実。 |
| 飲食店(レストラン・居酒屋) | 地元食材とのペアリングを楽しめる店が増加中。 |
| ブルワリー併設のタップルーム | 醸造所が併設された施設で、できたてをその場で味わえる。工場見学ができる場合も。 |
全国的にブルワリーの数も増えており、観光や出張の際に立ち寄ってみるのもおすすめです。
地域ごとのおすすめ店は別記事で紹介しています
初心者におすすめのクラフトビール5選
クラフトビールの世界は奥深く、味や香りのバリエーションも実に多彩です。
「気になるけど、どれを選べばいいかわからない」という方のために、初めてでも飲みやすく、入手しやすいクラフトビールを5本厳選しました。
1.よなよなエール(ヤッホーブルーイング)
ほどよいコクと華やかな香りが楽しめる、王道のペールエール。苦味も控えめで、クラフトビールの入り口として非常におすすめです。
全国のスーパーやコンビニでも入手できます。
2.水曜日のネコ(ヤッホーブルーイング)
ベルジャンホワイトスタイルの白ビールで、バナナやオレンジを思わせるフルーティーな香りが特徴。
ビールが苦手な人でも飲みやすく、「ビール=苦い」の印象が変わる1本です。
3.SPRING VALLEY シルクエール<白>(キリン)
なめらかな口当たりとやさしい甘みで、クセが少なくどんな食事にも合わせやすいビール。
大手メーカー製造で品質も安定しており、どこでも手に入れられる安心感があります。
4.TOKYO CRAFT ペールエール(サントリー)
柑橘系の香りが心地よく、後味はすっきり。クラフトビールの「香りの奥深さ」を感じられるバランスの取れた1本。
コンビニでも取り扱いがあり、手に入りやすいのも魅力です。
5.常陸野ネストビール ホワイトエール(木内酒造)
世界的にも評価が高い日本のクラフトビールブランド。やさしいスパイス感と爽やかな口当たりで、クラフトビールの華やかさを体験できます。
やや個性派ですが、「一歩踏み込んだ1本」としておすすめ。
クラフトビール選びのポイント
- 苦味が不安な方は「ホワイト系」や「ヴァイツェン系」から始めるのがおすすめ
- 「飲みごたえが欲しい」「香りを楽しみたい」という方は、ペールエールやIPA系も候補に
まずは、気軽に1本選んでみることがクラフトビールの世界への第一歩です。飲み比べセットや少量パックから試してみるのもいいでしょう。
「どれから試そう?」と迷ったら、スタイル別にセレクトされた飲み比べセットも選択肢の一つ。自分にぴったりの1本が見つかるかもしれません。
クラフトビールの楽しみ方
クラフトビールの魅力は、飲むだけでは終わりません。ちょっとした工夫や知識で、香りや味の楽しみ方が何倍にも広がります。
ここでは、注ぎ方や温度管理、料理との相性といった「自宅でできる楽しみ方」のポイントをご紹介します。
注ぎ方と温度管理のコツ
・注ぎ方の基本
グラスを45度に傾けて静かに注ぎ、最後に泡立てるようにまっすぐ注ぐことで、香りが立ちやすく、のど越しもスムーズになります。
・温度管理の目安
スタイルごとに適温が異なります。以下はあくまで目安です。
| スタイル | 特徴 |
|---|---|
| ヴァイツェン・ホワイトエール | 5〜7℃ |
| ペールエール・IPA | 7〜10℃ |
| スタウト・ダークエール | 10〜13℃ |
冷やしすぎると香りや甘みが感じにくくなるため、飲む10分前に冷蔵庫から出しておくのがおすすめです。
料理とのペアリングで、さらに美味しく!
クラフトビールは料理との相性(ペアリング)によっても魅力が引き立ちます。
ビールの個性と食材の風味がうまく重なると、味わいに相乗効果(マリアージュ)が生まれます。
| スタイル | 相性の良い料理の例 |
|---|---|
| IPA | 揚げ物、スパイシーな料理、グリル料理 |
| スタウト | チョコレート、ローストビーフ、煮込み料理 |
| ヴァイツェン | サラダ、魚介、フルーツ系デザート |
| ペールエール | ハンバーガー、ピザ、照り焼き |
ペアリングは“正解”があるわけではありません。自分なりの組み合わせを見つけるのも、クラフトビールの醍醐味のひとつです。
クラフトビールはなぜ高い? 価格の理由を解説
クラフトビールに興味を持ち始めた方の多くが、「美味しそうだけど、ちょっと高い…」と感じたことがあるのではないでしょうか?
ここでは、なぜクラフトビールの価格が高くなるのか、その理由をわかりやすく解説します。
大量生産ビールとのコスト構造の違い
クラフトビールは、原材料にもこだわっていることが多く、以下のようなコスト要因があります。
・高品質なホップやモルトを使用
アメリカやドイツなどからの輸入ホップや、地元産の特別な麦芽を使用することもあり、材料費が高くなります。
・小ロット醸造
定番商品でも数百リットル単位で醸造されることが多く、常に新鮮さを保つ分、在庫管理やロスリスクも増えます。
・流通の非効率性
大手のような全国ネットの販路がない場合には、1本ごとの流通コストが高くなりがちです。
これらを踏まえると、クラフトビールの価格は、一般的なビールと比べると高価ではあるものの、それは“手間と素材の違いによる正当な価格”と言えます。
少し高く感じるクラフトビールですが、製造の手間や素材の質を考えると納得の理由があります。賢く楽しむ方法もあわせて紹介しています
よくある質問
苦くないクラフトビールもある?
あります。
クラフトビール=苦いというイメージがあるかもしれませんが、実は苦味が少なく、フルーティーで飲みやすいスタイルも多くあります。
特に初心者には以下のようなスタイルがおすすめです。
• ヴァイツェン(小麦ビール):フルーティーで軽やか、苦味ほぼなし
• ホワイトエール:スパイスや柑橘香があり、やさしい味わい
• ベルジャンスタイル:やや甘みを感じる柔らかい口当たり
上で紹介した「水曜日のネコ」「常陸野ネスト ホワイトエール」などは、苦味が苦手な方にも人気です。
賞味期限はどれくらい?
一般的なクラフトビールの賞味期限は、製造から3〜6ヶ月程度です。
ただし、ブルワリーやスタイルによって異なり、要冷蔵の商品は特に新鮮なうちに飲むことが推奨されます。
また、開栓後はできるだけ当日中に飲み切るのがベストです。酸化によって香りや味が落ちやすくなります。
※裏面ラベルの「賞味期限」「要冷蔵」「濁りあり」などの表記は必ず確認しましょう。
Q. どれから飲めばいいかわからない
はじめての方には、以下のような選び方がおすすめです。
・定番の人気商品から試す
「よなよなエール」や「TOKYO CRAFT」など、スーパーで買える銘柄は飲みやすくバランスも良好。
・飲み比べセットを活用する
いろいろなスタイルを少しずつ試せるので、自分の好みに出会いやすい。
・「この香りが好き」「苦味は苦手」など、好みから逆引きする
サイトや専門店では、味の傾向別に紹介されている場合もあります。
最初の1本は“正解”を求めすぎず、気軽に選んでみるのがクラフトビールを楽しむ第一歩です。
良いクラフトビール・ライフを!
この記事では、クラフトビールの定義や種類などについて、初めての方にもわかりやすく解説してきました。
より詳しく知りたい方は、文中のリンク先もぜひ読んでみてください。
みなさまが良いクラフトビールに出会えることを祈っています!!