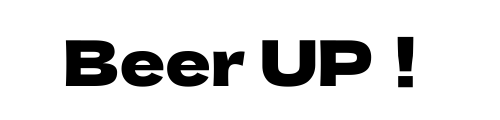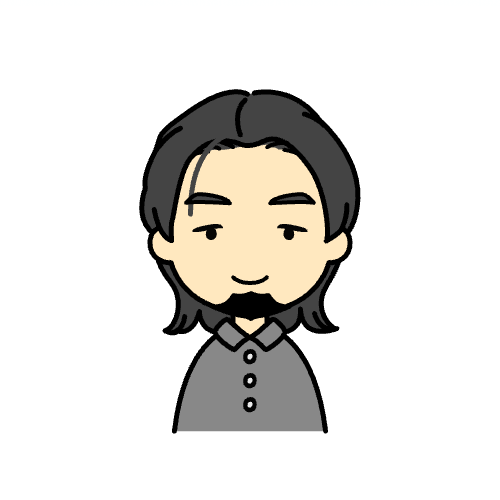「ビール」「発泡酒」「第3のビール」——スーパーなどで目にするこれらの名称、なんとなく価格が違うのは知っていても、「何が違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実はこの3種類、酒税法で定義が異なっており、使える原料や製造方法によって明確に分類されています。
この記事では、初心者でも理解しやすいように、3つの違いを図解・具体例つきで丁寧に解説。クラフトビールの話題にも触れながら、飲み比べのポイントや豆知識まで紹介していきます。
ビール・発泡酒・第3のビールの違いをざっくり比較!
成分と税制の違い
| 種類 | 原料と製法の特徴 | 麦芽使用率 | 税法上の分類 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ビール | 麦芽+ホップ+水 | 50%以上 or 副原料5%以内 | 発泡性種類(ビール) | コク・苦味が強く本格派 |
| 発泡酒 | 麦芽+副原料 | 50未満 or 副原料5%以上多め | 発泡性種類(発泡酒) | 極めてスッキリした味わい |
| 第3のビール | 大豆・コーンなど | 麦芽不使用 or 混成製法 | 発泡性種類 (その他の酒類) | 安価・クセが少なく飲みやすい |
税率は2023年10月の改正後、次のとおりです。
・ビール:約54.25円/350ml
・発泡酒:約46.99円/350ml
・第3のビール:37.80円/350ml
ビールの定義
スーパーやコンビニで見かける缶ビールの多くは、「ビール」「発泡酒」「新ジャンル(第3のビール)」と書かれていますが、これらはすべて、酒税法に基づいた分類です。
ここでは、酒税法上で定められた「ビール」の定義について、詳しく見ていきましょう。
麦芽・ホップ・水+「政令で定める副原料」が基本
酒税法では、以下の条件を満たす飲料が「ビール」として認められます。
- 原料:麦芽、ホップ、水、そして政令で定められた副原料
- 副原料の使用量:麦芽の重量の5%以内
- アルコール度数:20度未満
つまり、麦芽を主原料としつつ、ホップと水で発酵させた飲料に、ごく少量の副原料を加えたものが「ビール」となるのです。
副原料には、果物や香辛料、ハーブ、はちみつ、コーヒー、海藻類などが指定されています。これにより、多様な風味のビールが認められる一方で、使用量が5%を超えると「発泡酒」として分類される点に注意が必要です。
例:レモンピールやカモミールを少し加えたビールはOK。一方、フルーツピューレを大量に入れた場合、発泡酒に分類される可能性があります。
ビールの定義にある「政令で定める物品」とは!?
政府は、ビールに使える副原料(麦芽、ホップ、水以外の原料)として、次のものを定めています。
① 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮した果汁を含む。)
② コリアンダー又はその種
③ ビールに香り又は味を付けるために使用する次の物品
・ こしょう、シナモン、クローブ、さんしょうその他の香辛料又はその原料
・ カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
・ かんしょ、かぼちゃその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
・ そば又はごま ・ 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
・ 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品 ・ かき、こんぶ、わかめ又はかつお節
発泡酒の定義
ビールの条件を満たさないと「発泡酒」になる?
ビールと似た味わいのある飲料でも、酒税法上の定義に合致しない場合は「発泡酒」に分類されます。ここでは、発泡酒がどのような条件で定義されているかをわかりやすく整理してみましょう。
発泡酒に分類される主なケース
酒税法では、以下のいずれかに該当する場合、ビールではなく発泡酒として扱われます。
麦芽使用比率が50%未満副原料の使用量が麦芽重量の5%を超えるビールの製造に認められていない原料を使っている麦芽を使わず、麦を一部原料にしている
つまり、麦芽の割合が少なかったり、ビールで認められていない素材(例えば乳製品やチョコレートなど)を多く使ったりした場合、それは「発泡酒」となるのです。
味わいや自由度の違いも
発泡酒は、酒税法上のビールに比べて副原料の自由度が高いため、風味の幅が広がるという利点もあります。クラフトビールで「発泡酒」と記載されている銘柄があるのは、この自由度を活かしているからなのです。
第3のビールとは?
実は“ビール”じゃない?お得さの理由とは
「第3のビール」は、居酒屋やスーパーなどでも目にする機会が多い人気カテゴリですが、実は酒税法上では“ビール”にも“発泡酒”にも分類されない、特別な存在です。
正式には「新ジャンル」や「その他の発泡性酒類」と呼ばれ、次の2つのタイプに分けられます。
第3のビールの2つのタイプ
| タイプ | 原料・製法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 発泡酒+スピリッツ | 発泡酒に、焼酎やウォッカなどのスピリッツを加える | まろやかな味わい。比較的価格が安い |
| 大豆たんぱくなど非麦芽原料から製造 | 麦芽を使わず、大豆たんぱくやコーンなどを主原料とする | コクやキレに工夫あり。より低コストで提供可能 |
ビール好きにはどうなの? 味の満足度
第3のビールは、「価格重視で、ほどよくビール気分を楽しみたい」という方に最適です。
一方で、ビール特有のコクやホップの香りに物足りなさを感じる場合もあるため、クラフトビールや麦芽100%ビールを好む方には、ややライトな印象を受けるかもしれません。
クラフトビールは”ビールじゃない”ってホント!?
副原料の使い方で「発泡酒」扱いになることも
「クラフトビールは、実は“ビール”じゃない」──そんな話を耳にしたことはありませんか?
実はこれは半分本当で、半分誤解です。
クラフトビールとは、小規模な醸造所(ブルワリー)が独自のレシピで造る個性的なビールのこと。ですが、使われている原料の内容によっては、酒税法上「ビール」ではなく「発泡酒」に分類されることがあるのです。
※クラフトビールについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご一読ください。
副原料の量がポイント
酒税法では、「ビール」として認められるための条件として、次のようなルールが定められています。
- 麦芽、ホップ、水に加え、副原料(果実、ハーブ、スパイス等)を使う場合、麦芽の重量の5%以内であること
- 規定外の副原料(例:チョコレート、ミルクなど)を使うと、たとえ麦芽使用量が多くても「発泡酒」扱い
つまり、味わいや個性を追求するクラフトビールほど、「発泡酒」扱いになりやすいのです。
「発泡酒=安物ビール」ではない!
酒税法上の「発泡酒」という分類は、あくまで税制と原料構成に基づいた技術的な定義です。
「発泡酒だからクラフトビールの質が低い」というわけでは決してなく、むしろ発泡酒に分類されていても高品質でユニークな味わいのクラフトビールが多数存在しています。
例:クラフトビールとして知られる「水曜日のネコ」(ヤッホーブルーイング)は副原料にオレンジピールとコリアンダーシードを使っており、ビールファンにも人気の銘柄ですが、発泡酒に分類されます。
選び方のポイントと楽しみ方
どれを選ぶ?飲み比べのヒント
ビール系飲料は、「ビール・発泡酒・第3のビール・クラフトビール」と種類が多く、どれを選べばよいか迷う方も多いはず。味わいの傾向や価格帯が異なるため、シーンや好みに合わせた選び分けがポイントです。以下に、タイプ別の特徴とおすすめの楽しみ方をまとめました。
本格派は、やっぱりビールを!
麦芽比率が高く、ホップの香りや苦みがしっかりと効いた味わいが特徴です。ビール本来の深みを楽しみたい方や、食中酒として肉料理と合わせたいときにおすすめです。
コスパ重視なら発泡酒
麦芽使用量を抑えている分、価格が比較的安価で、のどごしも軽快。日常的に楽しむ“家飲みビール”として、気軽に手に取りやすいのが魅力です。
クセの少ないものを手軽に楽しみたい方は、第3のビール
原料や製法に工夫を凝らしてつくられる第3のビールは、クセが少なくあっさりとした味わい。ビール初心者や、苦みが得意でない方にも飲みやすいスタイルです。
個性を味わいたいなら…クラフトビール
小規模ブルワリーによる個性あふれる銘柄が多く、フルーティー、スパイシー、濃厚など多彩な味が楽しめます。ビールの新しい世界を知りたい方にぴったりです。
前述したとおり、税法上は、ビールに区分される場合と発泡酒に区分される場合があります。
クラフトビールを楽しむなら、税法上の区分は気にせずに!
このように、クラフトビールの中には酒税法上、ビールに分類されるものと発泡酒に分類されるものがあります。
もちろん、これらはあくまでも税法上の区分ですので「発泡酒だからクラフトビールらしくないのでは」といった表現が当てはまらないことは言うまでもありません。
実際、記事内で紹介した「水曜日のネコ」のほか、様々なクラフトビールが発泡酒扱いとなっています。
大事なのは、税法上の区分ではなく、自分に合ったビールを見つけること! 最近では、ビールの飲み比べセットなども手に入りやすいので、特に初心者の方はそうしたセットから好みを見つけてみるのも良いでしょう。
ご自宅や友人の家、はたまたキャンプなどでクラフトビールを飲む際、ネタのひとつとして、ビールや発泡酒の定義についてお話しするのも楽しいかもしれませんね。