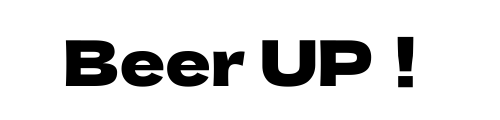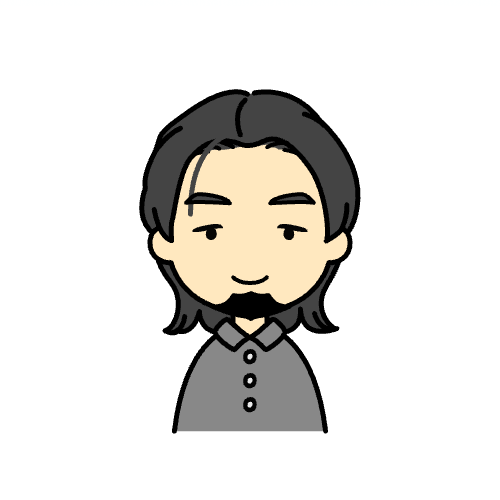クラフトビールを語るうえで欠かせないのが「原料」。
モルトやホップ、酵母といった素材が、香りや苦味、コクの違いを生み出します。
この記事では、クラフトビールに使われる代表的な原料と、それぞれの役割についてわかりやすく解説します。
「モルトって何?」「ホップはなぜ苦い?」といった疑問を持つ方も、この記事を読めばビールの味わい方が変わるはずです。
※クラフトビールそのものについて詳しく知りたい方は、「クラフトビールとは!? 初心者向けにわかりやすく解説!」もあわせてご覧ください。
クラフトビールの原料とは?
クラフトビールは、「モルト(麦芽)」「ホップ」「酵母」「水」の4つの基本原料からつくられています。
いずれも身近な素材ですが、それぞれの種類や使い方を変えることで、香り・色・味わいが大きく変化します。
| 原料 | 役割 | 味や香りへの影響 |
|---|---|---|
| モルト(麦芽) | 糖分を供給し、発酵の土台になる | 甘みやコク、色合いを決める |
| ホップ | 苦味と香りの付与、防腐作用も | 爽やかな苦味、柑橘・草のような香り |
| 酵母 | 発酵でアルコールを生む | 香りや口当たりに深く関与 |
| 水 | 原料の9割近くを占める | ミネラル量が味のバランスに影響 |
さらにクラフトビールでは、基本の4原料に加えて「副原料」を加えることで、個性豊かな味わいを演出することもよくあります。例えば、次のような素材です。
• 柚子や山椒などの和素材
• フルーツ、スパイス、ハーブ
• チョコレートやコーヒー豆、小麦、米
これらを活かすことで、飲んだ瞬間に「おっ」と驚くような、他にはない風味が生まれます。そのため、副原料は、クラフトビールの「自由さ」「遊び心」を象徴する存在と言えるでしょう。
このように、クラフトビールは4つの基本原料+副原料の組み合わせによって、無限のスタイルが生まれています。
【クラフトビールの原料①】モルト(麦芽)の役割と味への影響
モルトとは? 原料の基本と種類
モルトとは、大麦などの穀物を発芽させた後に乾燥させたものです。クラフトビールの主な糖分源となり、発酵によってアルコールや風味のベースを生み出します。
モルトには大きく分けて次の2種類があります。
ベースモルト(基本の糖分供給源)
例:ペールモルト、ピルスナーモルトなど
スペシャリティモルト(風味や色のアクセント)
例:カラメルモルト、ローストモルト、チョコレートモルトなど
ベースモルトは全体の90%以上を占めることもありますが、スペシャリティモルトを加えることで、香ばしさやコク、カラメル感などが生まれます。
<豆知識>
クラフトビールに使われているモルトまで注目すると、新たな楽しみが見えてくるかもしれません!
たとえば、ドイツのモルトメーカー「Weyermann」は、世界中のブルワリーで使われている代表的なブランド。特にヴァイツェンに使用される「Wheat Malt」は、柔らかい甘みと軽やかな口当たりで有名です。
色の違いで味が変わる?(ライト〜ダーク)
モルトの色は、SRM(Standard Reference Method)などで数値化され、そのままビールの色と深く関係しています。これは、焙煎度合い(麦芽を熱風で乾燥させるための施設=キルンの温度や時間)によって色が変わるためです。
| モルトの色合い | 焙煎度 | 味の特徴 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| ライト(明るい麦わら色) | 弱め | 軽やか、すっきり | ピルスナー、ヴァイツェン |
| ミディアム(琥珀〜銅) | 中程度 | カラメル感、甘み | ペールエール、 アンバーエール |
| ダーク(焦茶〜黒) | 強め | ロースト香、コク | スタウト、ポーター |
色だけでなく、口当たりや香ばしさ、ボディ感なども、使用されるモルトの種類で大きく変わります。
<豆知識>
「色が濃い=苦い」というわけではありません。ダークビールの多くは実は甘みが強く、苦味が控えめな場合もあります。色と味を切り離して捉えるのがポイントです。
代表的なスタイルとモルトの関係(ペールエール/スタウトなど)
ビールのスタイルごとに、よく使われるモルトの組み合わせがあります。ここでは、代表的な2つのスタイルを例に解説します。
ペールエール
• 主なモルト:ペールモルト(ベース)+クリスタルモルト
• 味の特徴:ほのかなカラメル感とすっきりした飲み口
• モルト比率:約90〜95%がベースモルトなのが一般的
イギリス由来のペールエールは、香りと飲みやすさのバランスを大事にしつつ、ホップとの相性を活かす配合が一般的です。
スタウト
• 主なモルト:ローストバーレイ、チョコレートモルト、ブラックモルト
• 味の特徴:コーヒーやカカオのようなロースト香、ほろ苦さ
• モルト比率:最大20%程度がスペシャリティモルト
スタウトは、焙煎モルトによる“焦がし感”が命。まるでコーヒーを思わせる奥行きのある風味が楽しめます。
【クラフトビールの原料②】ホップの特徴とクラフトビールへの効果
ホップとは?苦味だけじゃない香りの魔法
ホップは、ビールに欠かせない4つの主原料のひとつ。もともとは防腐効果を目的に使われ始めましたが、今では「苦味」や「香り」を与える存在として欠かせない存在になっています。
ホップが加わることで、ビールに爽やかなキレとバランスが生まれ、甘みのあるモルトと調和します。さらに、種類によっては柑橘やハーブ、トロピカルフルーツのような個性的な香りを与えてくれることも。
「香りがいい」と感じるクラフトビールの多くは、ホップの力によるものです。
<豆知識>
アメリカ農務省(USDA)やホップ栽培企業(Yakima Chief Hops等)は、ホップ品種ごとの香り特徴を「シトラス」「松」「スパイシー」など多彩に分類して紹介しています。ホップのキャラクターはワインのブドウ品種に似て、ビールの個性を左右します。
ホップの種類(アロマ/ビター系など)
ホップは、大きく「ビタリングホップ(苦味用)」と「アロマホップ(香り用)」の2つに分類されます。
| 種類 | 主な使用目的 | 特徴的な品種例 |
|---|---|---|
| ビタリングホップ | 苦味を与える | マグナム、コロンバス |
| アロマホップ | 香りを加える | カスケード、モザイク |
| デュアルパーパス | 苦味と香りの両方 | シトラ、シムコー |
クラフトビールでは、アロマホップやデュアルパーパスホップがふんだんに使われ、香りが主役になることも珍しくありません。
ホップは収穫された年や産地によっても香りが微妙に異なり、「同じ品種でも味が違う」といったワインのような楽しみ方も可能です。
IPAでホップを楽しむ
ホップの魅力を最大限に楽しめるスタイルといえば、「IPA(インディア・ペールエール)」。
特に「シトラ(Citra)」というホップ品種は、IPAでよく使われる代表格で、グレープフルーツやライムのような柑橘系アロマが特徴です。名前の通り「シトラス(柑橘)」をイメージさせる強烈な香りで、初めて飲むと驚く方も多いです。
<豆知識>
米国Brewers Associationの資料によると、近年最も多く使われているホップはCitra、Mosaic、Cascadeの順で、IPA市場の成長とホップ需要は密接に関係しています。[出典]
フレーバーホップ
苦味と香りづけに使用されるホップです。アロマホップよりも苦味成分の含有量が多く、香り成分も含んでいます。このホップで作られたビールはフルーティな香り、柑橘系の香り、スパイシーな香りなどが楽しめます。主にIPAやスタウトなどのバランスの取れたビールに使用されています。
マルトホップ
苦味成分の含有量が多く、香り成分はほとんど含んでいません。ビールに強い苦味を与えるため、ペールエールやスタウトなどの苦味の強いビールによく使用されます。
ホップは味わいや香りだけでなく、ビールの保存性にも影響を与えます。これは、ホップに含まれるタンニンは、ビールの酸化を防ぐ働きがあるためです。そのため、ホップを多く使用したビールは、保存性が高くなります。
【クラフトビールの原料③】酵母の違いが「スタイル」を生む
クラフトビールの味わいは、原料だけでなく「酵母」の違いによっても大きく変わります。発酵中に糖をアルコールへと変えるこの小さな存在が、ビールのスタイルを決定づけるカギと言えます。
酵母の基本:ラガー酵母とエール酵母
クラフトビールに使用される酵母の種類としては、次の2つがあります。どちらを使うかで、仕上がるビールの「方向性」がまったく異なります。
| 酵母の種類 | 発酵の特徴 | 代表的なスタイル |
|---|---|---|
| ラガー酵母(下面発酵) | 低温(7〜13℃)でタンクの底に 沈む | ピルスナー、ヘレス |
| エール酵母(上面発酵) | 高温(15〜25℃)でタンクの上に浮く | IPA、スタウト、ペールエール |
ラガー酵母(下澄み酵母・下面発酵酵母)
ラガー酵母は、下面発酵酵母とも呼ばれ、下面に沈んで発光する酵母です。下澄み発光酵母とも呼ばれます。
エール酵母と違って、香りやコク成分を生成しないため、すっきりした味わいのビールを生み出すのが特徴です。ピルスナービールやスタウトなどのラガービールなどによく使用されます。
一般的に8〜15℃で発酵させ、4週間〜6週間程度で発酵が完了します。
エール酵母(上澄み酵母・上面発酵酵母)
エール酵母は、上面発酵酵母とも呼ばれ、上面に浮かんで発酵する酵母です。上澄み発酵酵母とも呼ばれます。
ホップの香り成分を分解する際に香り成分を生成すること、また、タンパク質を分解する際に、コクのある成分を生成することから、フルーティな香りとコクのあるビールを生み出すのが特徴です。ペールエールやIPAなどのエールビールなどによく使用されます。
一般的に15〜25℃で発酵させ、2週間〜3週間程度で発酵が完了します。
発酵温度による味の違い
酵母は生き物。発酵温度が少し違うだけで、出す風味も大きく変化します。
• ラガー酵母(低温)
→ 雑味が少なく、キリッとした飲み口に。
→ 高温では働かず、発酵にも時間がかかる(そのぶん、すっきり仕上がる)。
• エール酵母(高温)
→ 発酵が早く、フルーティで複雑な香りを生成。
→ トロピカル、バナナ、クローブのような香りが出ることも。
たとえば、ヴァイツェンビールで感じるバナナ香は、酵母由来の「エステル」と呼ばれる成分によるものです。
セゾン酵母やワイルド酵母って何!?
クラフトビールの世界では、ラガー・エール以外にも個性派の酵母たちが活躍しています。
セゾン酵母
• 元はベルギーの農家が夏に飲むために仕込んだ「セゾンビール」用。
• 高温でも元気に発酵し、スパイシーでドライな仕上がりに。
• ペッパーやクローブのような香りが特徴。
ワイルド酵母
• ワインやベルギービールに使われる、自然由来の「野生酵母」。
• 独特の酸味や“ファンキー”な香り(干し草、革、ブルーチーズのような)を生み出す。
• 一般的なビールとは一線を画す、通好みの味わいに
→代表的なのは、オードグーズやランビックなど、ベルギーの伝統的サワーエール
【クラフトビールの原料④】ビールの味を左右する“水”の存在
クラフトビールの味を決めるうえで、意外と見落とされがちなのが「水」です。実は、ビールの約90%以上は水。どんな水を使うかによって、口当たりや味の印象は大きく変わります。
硬水・軟水の違いと味わいへの影響
| 種類 | 発酵の特徴 | 代表的なスタイル |
|---|---|---|
| 軟水 | ミネラル分が少ない | まろやかな味わい。ピルスナーやヴァイツェンなど、繊細なスタイルに向いている |
| 硬水 | ミネラル分が多い (特にカルシウム・マグネシウム) | シャープでキレのある味わい。IPAやペールエールなど、ホップの苦味が際立つビールに適している |
たとえば、チェコのピルゼン地方は「超軟水」で有名で、これが繊細で滑らかな「ピルスナー」の味を支えています。
一方、イギリスのバートン・オン・トレントの水は硬水で、ホップの苦味がよく映える「ペールエール」に最適。そのため「バートン化(Burtonization)」という水処理手法が確立されたほどです。
土地ごとの水とスタイルの関係
ビールの歴史をたどると、その土地の水質がスタイルの誕生に深く関わっていることがわかります。
• ドルトムンダー(ドイツ・ドルトムント)
→ 中程度の硬水が生み出す、バランスのとれた味わい。ラガーの中でも麦のコクと苦味が調和したスタイル。
• バートン・オン・トレント(イギリス)
→ 高硬度の水が特徴で、ホップの苦味と香りを際立たせるペールエールの名産地。現代のクラフトIPAにも影響を与えた“水の聖地”ともいえます。
• ピルゼン(チェコ)
→ 超軟水により、苦味が抑えられたクリアな味わいのピルスナーが誕生。世界中で愛されるスタイルの原点。
硬度が高い水は、ビールの味わいにコクやボディを与え、硬度が低い水は、ビールの味わいをすっきりとさせます。
一方、ミネラル分(カルシウムやマグネシウム、ナトリウム)の量も、ビールの味わいに影響を与えます。カルシウムは、ビールの泡立ちをよくし、マグネシウムは、ビールの苦味を強くします。また、ナトリウムは、ビールの味わいを塩辛くします。
【クラフトビールの原料⑤】副原料と個性派クラフトビール
クラフトビールの楽しさのひとつが、「こんなものまで!?」と思うような副原料の使い方です。
モルト・ホップ・酵母・水という基本の4つの原料に加え、フルーツやスパイス、コーヒー、チョコレートなど、自由な発想でつくられたビールがたくさんあります。
副原料が加わることで、味や香りの幅がぐっと広がり、個性的な1本に出会えることも。ここでは、どんな副原料が使われているのか、そしてどんなスタイルに活かされているのかをご紹介します。
フルーツ、スパイス、コーヒーなどの使用例
副原料は、ビールの味や香りを際立たせるために使われます。代表的な使用例は次のとおりです。
| 副原料 | よく使われるスタイル | 味・香りの特徴 |
|---|---|---|
| フルーツ (オレンジ、ゆず、桃など) | ホワイトエール、フルーツエール | 甘酸っぱさや華やかな香りが加わる |
| スパイス (コリアンダー、シナモンなど) | セゾン、ホワイトエール | 爽やかさやスパイシーな余韻が特徴 |
| コーヒー/チョコレート | スタウト、ポーター | 焙煎香が深く、デザートのような 味わいに |
| ハーブ・お茶類 (ローズマリー、緑茶など) | ハーブエール、実験的なスタイル | 和洋問わず個性を活かした香りづけが可能 |
<豆知識>
たとえば、ヤッホーブルーイングの「水曜日のネコ」にはオレンジピールとコリアンダーシードが使われており、香り高く爽やかな飲み口が特徴です。
副原料による個性的な味
副原料は、スタイルによって使われ方が異なるのもポイントです。
サワーエール系
乳酸菌などを使って酸味をつけるビール。そこに果実(ベリー類や柑橘など)を加えることで、甘酸っぱい味わいに。ビールというより“クラフトカクテル”のような印象を受けることもあります。
例:志賀高原ビール「SALTY HOP」は、柚子と塩を使った爽やかなフルーツサワーエールです。
セゾン
ベルギー発祥の農民ビールで、もともとは夏場の喉を潤す目的で造られたため、スパイスやハーブなど、副原料の自由度が高いのが特徴。
例:栃木県のうしとらブルワリーでは、多様なセゾンをリリースしており、柚子・山椒・ジンジャーなどの和素材を活かしたユニークなビールを展開しています。
原料から読み解く! クラフトビールの楽しみ方
ラベルから分かる、原料情報の見方とは
クラフトビールのボトルや缶には、製造者名やアルコール度数だけでなく、使用されている原料(モルトやホップ、副原料など)が記載されています。
実はこれ、ビール選びのヒントになる情報の宝庫です。たとえば以下のようなポイントに注目してみましょう。
| 表記例 | 読み解きポイント |
|---|---|
| 使用ホップ:Citra, Mosaic | 柑橘系の香りやトロピカルなアロマが 楽しめる可能性が高い |
| モルト:Pale Ale Malt / Chocolate Malt | 淡い色なら軽めの味、焦がし系なら ロースト感のある香ばしさに期待 |
| 副原料:オレンジピール、コリアンダー | 爽やかでスパイシーな香りがアクセントに |
また、「IBU(International Bitterness Units)」という苦味の目安が書かれている場合もあり、数値が高いほど苦味が強い傾向があります。
最近では、ホップの種類や産地にこだわるブルワリーも多く、「このホップが好き」という発見を重ねていくと、自然とビールの選び方も洗練されていきます。
自分好みの原料の傾向を見つけよう
ビールの好みは、「苦い or 甘い」「軽い or 濃い」といった味の印象だけでなく、使われている原料の特徴にも大きく影響されます。
たとえば…
• ホップが気になる人 → IPAやペールエールで柑橘系や松のような香りを楽しむ傾向あり
• モルトが気になる人 → スタウトやアンバーエールなど、香ばしくコクのあるビールを好むことが多い
• 副原料が気になる人 → サワーやセゾンで、果実やスパイスのアクセントを探すのが楽しみ
最初は、「この銘柄、美味しかったな」と思ったビールのラベルを記録しておくのがおすすめです。そこから、「共通して使われているホップがある」「副原料にフルーツが多い」といった自分の好みの傾向が見えてくるはずです。
<豆知識>
最近では、飲んだビールの原料や評価を記録できるアプリも登場しています。初心者の方は、こうしたアプリを活用すると、クラフトビールを選ぶのがより楽しくなってきます!
よくある質問
Q. モルトと麦って同じ?
A.モルトは“麦芽”のことで、麦を発芽させて乾燥させたものです。
つまり、麦(おもに大麦)を加工してできたのがモルト。これを煮出して糖分を抽出し、酵母によってアルコールに変えていきます。
モルトの種類や焙煎具合によって、ビールの「色」や「甘み」「コク」が大きく変わるため、クラフトビールの“味の土台”といえる存在です。
Q. ホップって植物?どこで育つの?
A. ホップはビール専用の“つる性植物”で、松ぼっくりのような形の花を使います。
香りづけと苦味の調整のために使われるホップは、世界中で品種改良が進められており、代表的な産地としては以下のような場所があります。
アメリカ(ワシントン州など):柑橘・トロピカルなのが特徴
ドイツ:上品な草やハーブ系が特徴
日本(岩手・秋田・長野など):国産ホップの栽培も拡大中。爽やかで穏やかな香りのものが多い。
Q. ビールに酵母が残ってるとどうなる?
A. 濾過せずに酵母が残っているビールは、風味がまろやかになったり、自然な炭酸が生まれたりします。
クラフトビールでは、あえて酵母を完全には取り除かず、「瓶内二次発酵」を利用して微炭酸を作ることもあります。
これにより、
• 味わいに深みが出る
• 酵母由来の香り(バナナやクローブなど)を楽しめる
• 賞味期限が比較的短めになる(生きた酵母が変化を続けるため)
といった特徴が出てきます。
ちなみに、グラスの底に沈んでいる“にごり”は、酵母やタンパク質の成分。体に悪いものではありませんが、風味にクセが出ることもあるため、好みで飲み方を調整してOKです。
原料にも注目することで、クラフトビールを飲むのがより楽しくなる!
ここまで、クラフトビールの原料について解説してきました。
クラフトビールを購入する際には、これらの原料にも注目してみると、自分好みの味わいや香りを知るための大きなヒントになるはずです。
原料を深掘りして、よりクラフトビール沼の奥深くへ踏み入ってみてはいかがでしょうか。